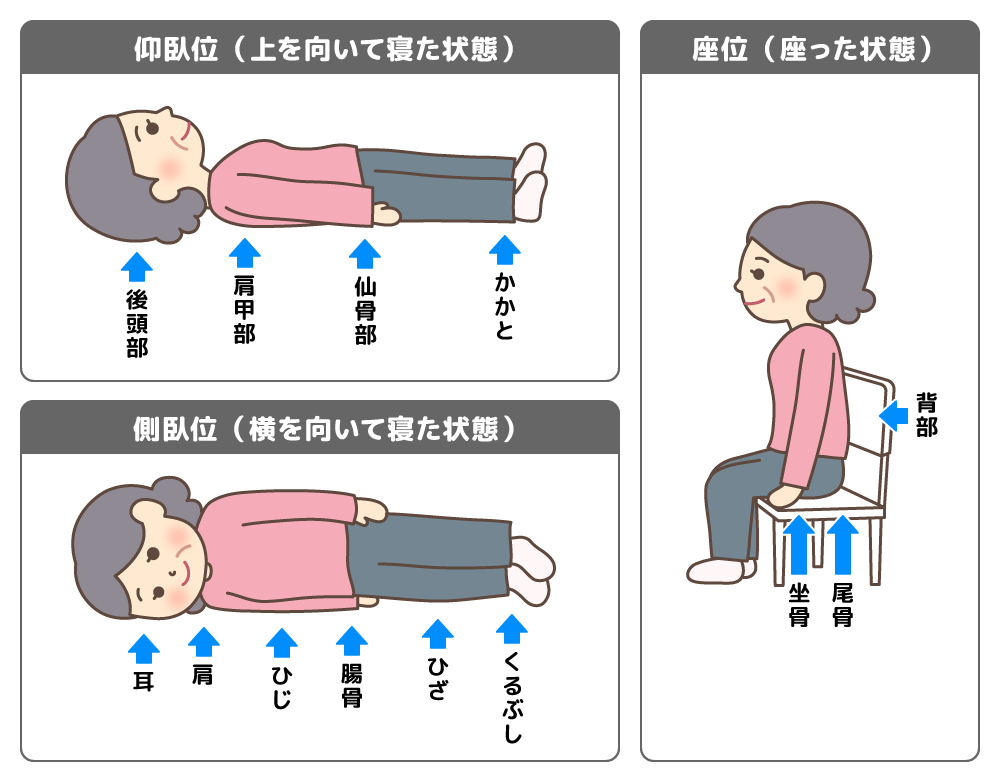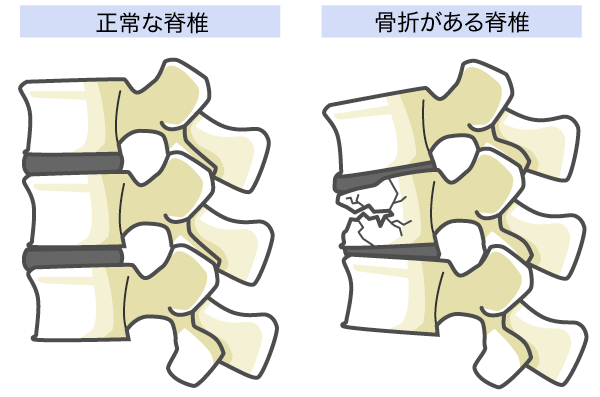7月も後半になり、じめじめした梅雨から、今年も猛暑の夏がやってくるのでしょうか・・・。
このブログを書いている今日は、九州地方が梅雨明けしたというニュースが入ってきました。ということは、このブログが掲載されている頃、沢渡も猛暑に襲われていないことを願っています。
今年も後半に入り、今年前半を振りかえる方、後半戦を頑張ろうと改めて気を引き締める方、などなど皆さん、毎日を色々な気持ちで過ごされているかと思いますが、「自分を労る」ということについて、お話しできたらと思います。
仕事・家庭・プライベート・・・。 1日の中で1人の人間が様々な立場で生活し、活動しています。その中で頑張りすぎると、何となく空回りして物事が上手くいかないような感じになる事はありませんか?また、先程も書いたのですが、今年前半や何か区切りの時に、自分を振り返って「上手くいかなかったな~。」と落ち込み気味になる事もありませんか?
そのようなとき、人間は「自分を責める」という感情を持つようです。そうすると、いわゆる「負のループ」というものに陥り、自分の周りで起きることを悪く捉えがちになってしまいます。そうなると、抜け出す方法が見えなくて、辛いですよね。そのときに「自分を労る」ということを考えていくと、その負のループから抜け出せるようになるとのことです。
人間は、「分かってもらいたい」「認めてもらいたい」という欲求を当たり前に抱くもので、それを「承認欲求」と言います。承認欲求には、他者から得られる「他者承認」、自分で自分を認める「自己承認」があります。
大人になると、褒めてもらう機会って、なかなか無いですよね。また、相手が褒める部分と自分が褒めて欲しい部分に乖離が生じます。自分が望むように褒めてもらえるということは、なかなか難しいですよね。
そのため、「他者承認」にのみ依存している人は、「褒めてもらいたいから自慢話をする。」「褒めてくれないと、やる気が出ない。」と、他者からの評価のみが、自分の評価になってしまいます。
一方、自己承認ができると、他者からの評価に依存することなく、精神的に自立することができるため、とても生きやすくなります。

でも、承認欲求を満たすのって難しいですよね。今回は承認欲求を満たすといわれる方法を1つ紹介したいと思います。
≪自分褒めワーク≫(「ホメ療法」とも言われているようです。検索するとでてきます。)
進め方としては、
①1日を振り返り、できたことを3つあげる
②褒め言葉を加えて
③アウトプット(書くor話す)する
※1日の終わりに行うのがおすすめとのことです。
○アウトプットするときのポイントです。
★褒め言葉を必ず加えること
★頭の中で考えるだけでなく、アウトプット(書くor話す)すること
→視覚・聴覚から情報を再度インプットすることで、承認欲求が確実なものになるそうです。
○アウトプットの例として…
・今日は、連休明けなのに時間通り出勤できた。よく頑張った!
・優先順位を考えて、「○○をやらない」と決断できた。自分賢い!
・自分から挨拶できた。自分えらい! などなど…
自分ができたこと、何でもいいので「いいね!」をつける感じでするといいようです。
「そんなこと言っても、たいしたことじゃない…。」と思うことでも、気にする必要はないようです。
あくまで自分褒めワークなのですから些細なことで大丈夫です。むしろ、誰も褒めてくれないことに気付けるのは自分だけですので、思い切って自分を褒めまくりましょう。
特に日本人は、幼いころから完璧を求められ、忘れ物をしない・遅刻をしない・満点をとれてこそ価値があるという風潮が強い傾向があります。理想的な姿を追求することは素晴らしいのですが、完璧でなければ認められないという思考は、自分を苦しめてしまいます。
欠けた部分にフォーカスするのではなく、意識的にできている部分にフォーカスし、自分自身で認めていく作業を行うことで、
「不完全でOK」→「そんな自分を丸ごと受けとける」→「そんな相手を許す」
という考えができていくといいですね。
この考えが定着すると、臨床で関わる患者さんやスタッフにも、もっと感謝して関われるようになるかな、と思いました。
自分が疲れたな、やる気が出ないな、と思ったら、ちょっと試してみて下さい。意外と自分自身の見方が変わってくるかもしれません。
最後に、「自分を労る」ということで、ちょっとオススメの本があるので紹介したいと思います。
「アイシナモロールと”一緒にご自愛“ ~自分を好きになるための56のコツ~」
中島輝 著 (扶桑社)

「シナモンロール」というキャラクターをご存じですか?その「シナモンロール」の友達の「アイシナモロール」が、「自分を大事にする方法」についてお話を進めています。目次から、自分の読みたいところを選べるところもあるため、簡単に読むことが出来ます。疲れた頭を休めるには、ちょっと良いかもしれません。もし気になる方がいましたら、通販サイトなどで簡単なあらすじも読めますので、参考にどうぞ。
記事担当:OT唐澤恵美